~広島で個人再生を検討する皆さまへ~
個人再生とは?
個人再生は、裁判所を通じて借金を大幅に減額し、3~5年で分割返済を行う債務整理の手続きです。
特に、住宅ローンがある場合でも自宅を維持できる点が大きな特徴です。
借金問題で相談を受けた際、まず破産を検討することが一般的です。
破産は借金の返済を免除してもらう手続きであり、多くのケースで最適な選択肢となります。
しかし、以下のような事情がある場合は、個人再生を選択することになります。
- 住宅ローンのある自宅を手放したくない
- 破産による職業制限を受ける
- ギャンブルなどの免責不許可事由に該当し、免責が認められない可能性がある
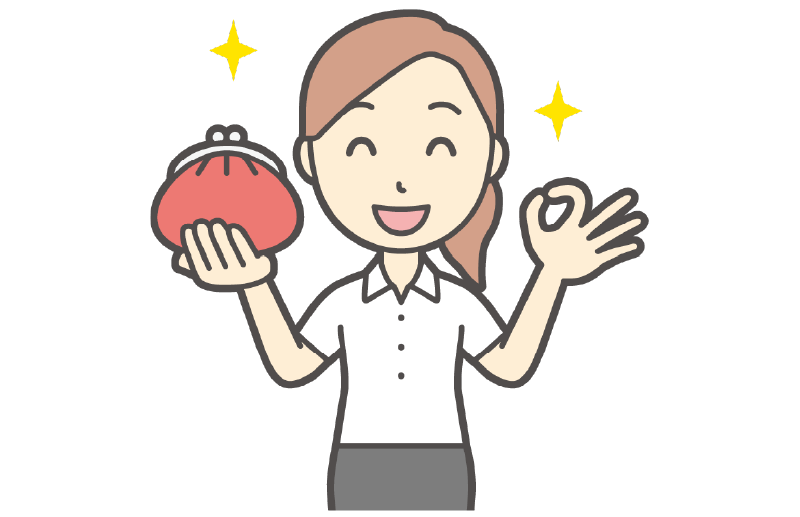
個人再生が向いている方
個人再生は、以下のような方に適した債務整理方法です。
(※一定条件を満たす必要があります。)
- ローン返済中の住宅を残したい方
- 自己破産できない事情(免責不許可事由など)のある方
個人再生のメリット・デメリット
メリット
- 借金を大幅に減額できる(最大1/10)
- 住宅ローン特則を使えば自宅を維持できる
- 破産のような職業制限がない
- 財産を処分する必要がない(清算価値基準という基準を満たす必要があります)
デメリット
- すべての借金が対象ではない(税金や養育費は減額不可)
- 定期的、継続的な収入がないと手続きを利用できない
- 手続きが複雑で時間がかかる
- 5,000万円を超える借金があると適用不可
住宅ローン特別条項の利用
個人再生の「住宅ローン特別条項」を利用すると、住宅ローンの支払いを継続しながら、その他の借金のみを大幅に減額できます。
ただし、適用には条件があり、住宅ローンの担保が設定された自宅であること、本人または家族が居住していることなどが求められます。
住宅ローンそのものの減額はできませんが、返済期間の延長などで負担を軽減する方法もあります。
個人再生の手続きの流れ
- 弁護士へ相談し、個人再生の適用可否を判断
- 弁護士が債権者へ受任通知を送付(取り立て・督促が停止)
- 債権調査・必要書類の収集(給与明細、住民票、財産資料など)
- 裁判所への申立て(審査後、手続開始)
- 再生計画案の作成・提出(減額後の返済計画を策定)
- 債権者の意見聴取・裁判所の認可
- 減額後の借金を3~5年で分割返済(申立から約半年後に開始)
小規模個人再生と給与所得者等再生
個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類があります。
小規模個人再生
- 将来にわたり継続的な収入があれば利用可能(アルバイトやパートでも可)
- 借金総額に応じて返済額が決定(例:600万円の借金なら120万円)
- 債権者の同意が必要
給与所得者等再生
- 定期的な収入があり、収入変動が小さいことが条件(小規模個人再生より基準が厳しいです)
- 可処分所得2年分が最低返済額(例:可処分所得2年分が300万円なら返済額300万円)
- 債権者の同意が不要
多くの場合、小規模個人再生の方が返済額が少なく有利ですが、債権者の同意が必要です。
債権者の反対が予想される場合は、給与所得者等再生を選択することになります。
個人再生で、借金はどれくらい減るか
- 小規模個人再生では、借金を5分の1〜10分の1(最低額100万円)に減額し、残りを3〜5年程度で返済する計画を立てます。
- 給与所得者等再生では、実質的な可処分所得(給与から社会保険料や税金などを差し引いた金額)から政令の定める最低生活費を引いた金額の2年分を返済する計画を立てます。
前記のとおり、小規模個人再生の方が弁済額が少なくなることが多いです。
ただし、いずれの方法でも清算価値保証原則という原則があり、上記の基準よりも手持ちの資産が多い場合は、その資産の評価額の総額が最低弁済額となります。

個人再生以外の解決方法
比較的手続が容易な「任意整理」や借金の返済を免除してもらうことことのできる「自己破産」という手続もあります。
(※詳細を知りたい方は、お気軽にご相談ください。)
まとめ
個人再生は、住宅を維持しながら借金を整理できる有効な手続きですが、適用条件や手続きが複雑となります。
破産や任意整理と比較してどの手続きを選択するかは、収入状況、債務の額、借り入れの原因、債権者の対応等によって異なりますので、個人再生を検討されている方は、まずは専門家に相談することをおすすめします。
